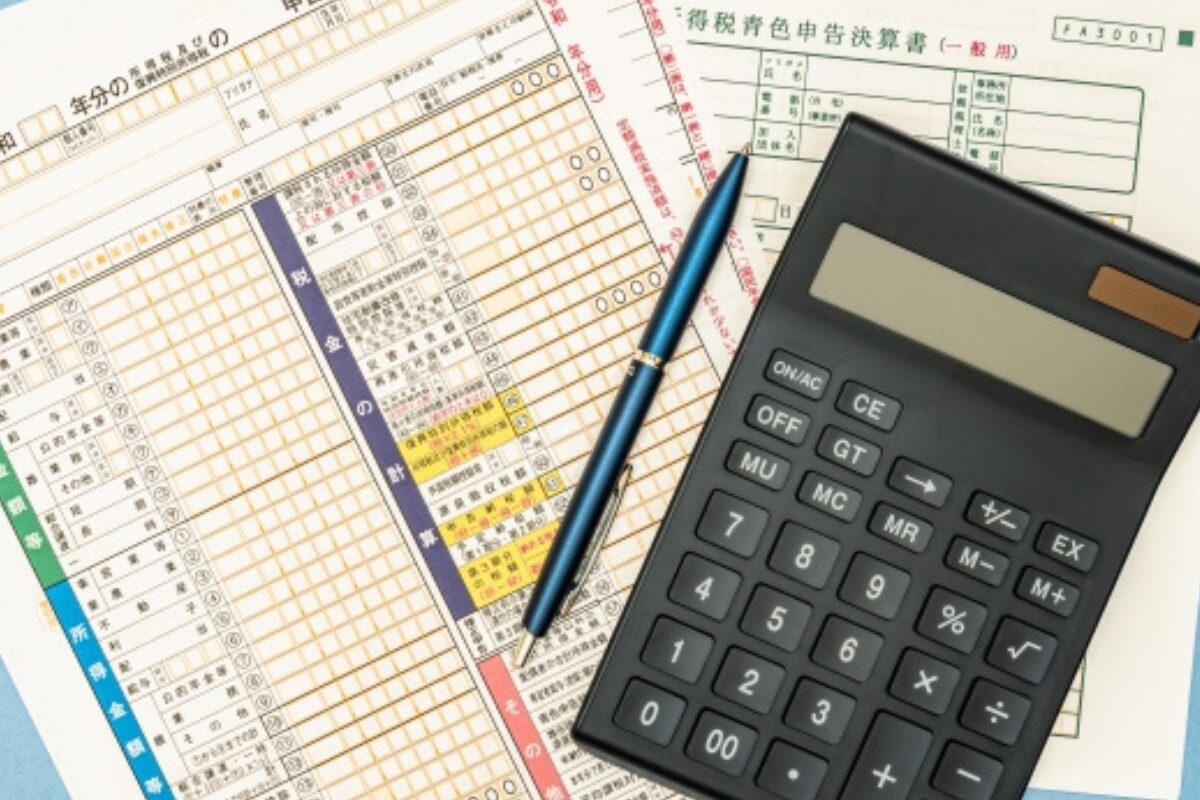副業で稼ぎ始めた30代サラリーマンにとって、避けて通れないのが税金。
知らなかったでは済まされない、所得税・住民税・社会保険料のしくみを正しく理解しておかないと
想定以上の税金を取られたり、住民税の通知で副業が会社にバレるリスクもあります。
この【税金大全】では、副業で収入が出始めたサラリーマンに向けて、税金の基本をわかりやすく整理しました。
副業で所得税や社会保険料があがる?
副業がバレないようにする方法
いくら稼いだらいくら上がる?
どうやって帳簿をつける?
確定申告のやり方
帳簿や申告に時間をかけたくない
青色申告?白色申告?
税務調査がくるケース
税務調査のペナルティ
副業リーマンができる節税
副業リーマンに関係がある税金は?
この大全だけで完結できる内容になっていますので、税金のしくみと対策が理解できて、安心して副業に集中できるはずです。
- 30代後半から2回の転職に成功
- 副業歴7年
- 投資歴12年
- 税務歴5年
- 妻・子ども2人
- 30代副業サラリーマンです
税金の種類(副業初心者向け)
副業を始めたサラリーマンにかかわる税金は3つです。
| 種類 | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得税 | 課税所得 (所得から控除を引いたもの) にかかる税金 | 5%〜45% |
| 住民税 | 前年の課税所得 (所得から控除を引いたもの) にかかる税金 | 約10% |
| 社会保険料 | 健康保険・年金 雇用保険の保険料 | 約15% |
副業が軌道に乗ると、これらに加えて、消費税、事業税がかかわってきます。
しかし、それは稼げるようになってからの話ですので今は気にしなくても大丈夫です。
副業が軌道に乗るほど、税金対策もより重要に。
まずは、それぞれの税金について見ていきましょう。
所得税
所得税は、ざっくり言うと儲かったお金にかかる税金です。
サラリーマンの場合、毎月の給与から源泉徴収として引かれています。
所得税が決まる2つの要素
給与や副業の収入から経費や控除(基礎控除・医療費控除など)を引いた金額
課税所得に応じて段階的に上がる掛率(5~45%)
つまり
収入が増える=そのまま税金も上がる
わけではなく
収入から経費や控除を引いた実質のもうけに対して税金がかかるという仕組みです。
所得税の税率表
所得税は稼げば稼ぐほど税率が上がっていきます。
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※それぞれの税率は超過部分に適用されます。例えば、課税所得額500万円の場合、500万円全体に20%がかかるわけではありません。
330万円を超えた部分からの170万円に対して20%かかります。
わかりやすくするためにそれぞれに控除額が設定されています。
実際の税額は
5,000,000円 × 20% – 427,500円 = 572,500円
課税所得額が500万円に対して所得税は572,500円になります。
副業で所得税が増える?
はい、増えます。
副業で利益が出た場合、その分、課税所得が増える=所得税も増えるということ。
副業で稼ぐ=税金も上がるという感覚を持っておきましょう。
逆に言えば、必要経費や控除を活用することで、課税所得を減らすことも可能です。
副業を始めるときは、稼ぐだけでなく「どうやって税金をコントロールするか」も意識することも大切です。
住民税
住民税は所得税と同じように儲かったお金に対してかかる税金ですが、翌年に支払うという時間差で請求がくるものです。
また、住民税とは、市役所などに支払う税金です。(市県民税・市民税とも呼ばれます)
所得税が「国」に納める税金なのに対して、住民税は「地方」に納める税金となります。
住民税が決まる2つの要素
住民税は、次の2つの要素から構成されています。
| 内容 | 税率・税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 一定の所得を超えるとかかる | 年額 約5,000円〜 6,000円 |
| 所得割 | 前年の課税所得にかかる | 10% |
たとえ課税所得額が0円でも、所得額が一定値を超えれば均等割は支払う必要があります。
例:課税所得額が120万円の場合
均等割(5,000円)+所得割(120,000円)=住民税額125,000円(年間)
- 均等割+所得割の人
- 均等割のみの人
- 非課税の人
住民税の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税額 | 前年の課税所得額で決まる |
| 税率 | 課税所得額の10% |
| 納付時期 | 毎年6月〜翌年5月までの1年間 |
| 徴収方法 | 特別徴収(給与天引き) 普通徴収(自分で支払う) |
副業で住民税が増える?
はい、増えます。
副業で年間20万円以上の所得(もうけ)があり、確定申告をおこなうと住民税にも反映されます。
たとえば本業で年収500万円、副業で30万円の所得がある場合、その副業分にも10%(3万円)の住民税が加算されます。
そして、ここで注意したいのが…
「副業バレ」のおもな原因は住民税
副業が会社にバレる一番多いケースが、住民税の通知額の不一致です。
会社では、本業の給与をもとに住民税を計算しているのに、市役所から通知される住民税額がそれより多いと、「この人、他にも所得があるな?」と経理担当に気づかれることがあります。
(実際には、ほとんどの会社はいちいち、あなたの住民税の計算はしておらず、市役所から届く、あなたの住民税額通知を見て、そのとおり毎月天引するだけですが、勘のいい経理担当者なら通知額を見ただけでわかる人もいます)
これを防ぐには確定申告のときに、住民税の支払い方法を副業分のみを「普通徴収(自分で納付)」に設定することができます。
こうすれば、副業分の住民税だけを自分で支払うことになるため、本業の会社には本業の給与分のみの住民税額が通知されます。
しかし、普通徴収(自分で納付)に設定していても予期せぬ事態がおこることがあります。
以下に記事をまとめました。

住民税は「前年の課税所得」をもとに決定されるので、副業所得があると税額も増える仕組みです。
節税のためにも、また副業バレ防止にも、課税の仕組みや支払い方法を理解しておくことが大切です。
他にも「副業バレ原因」はいくつかあります。
以下に副業バレ5つの原因の記事をまとめました。

社会保険料
社会保険料は、年金・健康保険・雇用保険などの保障制度を支えるために支払う保険料のことです。
サラリーマンの場合は、給与から自動的に天引きされるため、普段あまり意識することはないかもしれません。
ですが、この保険料、私たちの老後や病気・失業などに対して、将来の生活を守るために欠かせないものなのです。
サラリーマンとして働いている場合、社会保険料は会社と労働者が折半して負担しており、給与明細を見ると、その内訳(健康保険・厚生年金・雇用保険など)を確認できます。
おもに以下の5つが社会保険に含まれます。
社会保険の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険 | 医療費の自己負担を軽減 |
| 厚生年金 | 老齢年金や障害年金、死亡 時の遺族年金などの生活保障 |
| 雇用保険 | 失業した時の給付(失業手当) 再就職支援 |
| 労災保険 | 仕事中のケガや病気 通勤途中の事故などの補償 |
| 介護保険 (40歳~) | 要介護状態になったときの サービス利用を支援 |
給与が増えると社会保険料も増える理由
社会保険料は、あなたの給与(標準報酬月額)によって計算されるため、給与が増えるとその分、支払う保険料も増えていきます。
これは「比例負担」の仕組みになっており、給与が高くなるほど保険料も段階的に引き上げられる仕組みになっています。
社会保険料は標準報酬月額で決まる
サラリーマンの社会保険料は、毎月の給与(基本給+各種手当)をもとに決まる「標準報酬月額」という等級で決まります。
この標準報酬月額に保険料率を掛けることで、実際に支払う保険料が決まる仕組みです。
※各種手当には残業手当・休日出勤手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・役職手当などが含まれます。
そして重要なのが、毎年4月〜6月の給与をもとに、その年(9月から)の保険料が決まるという点。これを「定時決定・算定基礎届」と呼びます。
サラリーマンが社会保険料を安くする方法
たとえば、3〜5月にたくさん残業をしたり、手当が増えたりすると、それが給与に反映されて標準報酬月額が上がります。すると、その年の9月から毎月の社会保険料も高くなってしまいます。
一方で、この期間に残業を控えるといった対応をすることで、標準報酬月額の上昇を抑えることができ、結果として1年間の社会保険料を安くできることがあります。
手取りがあまり増えないと感じる理由
年収が上がったのに、思ったほど手取りが増えない…という声もよくありますが、その背景にはこの社会保険料や税金の増加が影響しています。
つまり、「年収アップ=そのまま手取りアップ」ではないということ。
しっかり収支を把握して、給与明細をチェックするクセをつけておくと、手取り感覚が養われます。
以下に早見表を掲載します。
税金+社会保険料+手取りの早見表
年収に対して手取り・税金・社会保険料の参考の概算表です。(扶養人数などによって変動します。)
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 控除合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万 | 約3万 | 約13万 | 約42万 | 約58万 | 約242万 |
| 400万 | 約6万 | 約20万 | 約62万 | 約88万 | 約312万 |
| 500万 | 約13万 | 約25万 | 約80万 | 約118万 | 約382万 |
| 600万 | 約21万 | 約30万 | 約102万 | 約153万 | 約447万 |
| 700万 | 約29万 | 約35万 | 約124万 | 約188万 | 約512万 |
| 800万 | 約38万 | 約40万 | 約144万 | 約222万 | 約578万 |
副業で社会保険料が増える?
いいえ、増えません。
副業を始めると「個人事業主」としての立場が加わることになりますが、本業でサラリーマンとして社会保険に加入している場合、副業に関しては基本的に追加で保険に加入する必要はありません。
ただし、本業を辞めて副業一本でやっていく場合は、「国民健康保険」と「国民年金」に切り替える必要があります。
なお、副業によって所得が増えても、会社の社会保険料は副業所得には影響されません。あくまで本業の給与に基づいて保険料が決まる仕組みになっています。
以下に副業と社会保険料の記事をまとめました。

控除
「控除」とは、所得税や住民税を安くするための割引のような制度です。
サラリーマンや副業をしている人も、この控除を上手に活用することで、納める税金を大きく減らすことが可能になります。
※控除は社会保険料とは無関係ですので、いくら控除をとっても社会保険料は安くなりません。
税金は基本的に、課税所得に対してかかりますが、控除によって課税所得自体を圧縮できるため、結果的に課税される金額も減少し、支払う税金も安くなります。
控除の種類
サラリーマンや副業初心者の方にかかわりが深い控除の一覧です。
| 控除の種類 | 内容 | 控除額 (所得税) | 控除額 (住民税) |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 誰でも受けられる基本控除 | 48万円 | 43万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得が48万円以下なら受けられる控除 | 最大38万円 | 最大33万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得が48万円〜133 万円の間で段階的に控除 | 最大38万円 | 最大33万円 |
| 扶養控除 | 扶養する家族(16歳以上)に 対して受けられる控除 対象の年齢や同居状況で変動 | 38万円〜63万円 (一人につき) | 33万円〜45万円 (一人につき) |
| 社会保険料控除 | 健康保険、年金、雇用保険の 支払額が全額控除 | 支払額の全額 | 支払額の全額 |
| 生命保険料控除 | 民間の生命保険などに加入 している場合に適用 | 最大12万円 (最大4万円×3区分) | 最大7万円 (最大2.8万円×3区分) |
| 医療費控除 | 医療費が10万円または所得の 5%を超えた場合、超過分 を控除 | 超過分 (上限200万円) | 超過分 (上限200万円) |
| 寄附金控除 (ふるさと納税) | 寄附金のうち2,000円を 超えた分が控除対象 | 所得控除または 税額控除 | 税額控除 (上限あり) |
副業する人の「経費」と「控除」
副業を始めた人にとって特に重要なのが、経費の考え方です。
これは、副業にかかった費用を控除のように扱って所得を減らすことができるので、しっかり記録しておけば節税に大きく貢献します。
たとえば、副業で使った以下のような支出が経費になる可能性があります。
- パソコン・スマホ代
- 通信費
- 書籍やセミナー代
- カフェでの打ち合わせ費用
- 交通費や外注費 など
以下に経費の考え方の記事をまとめました。

これらの支出は、帳簿をつけて記録し、確定申告で「経費」として計上する必要があります。
収入がでたら帳簿をつけよう
副業で収入が発生したら、必ず帳簿をつけておきましょう。帳簿には「いつ」「いくら」「どこから」収入があったかを記録します。
確定申告や経費計上に必要な情報になるだけでなく、自分のビジネスの収支を把握するためにも欠かせません。
手書きでもExcelでも、クラウド会計ソフトでも大丈夫です。早めに習慣化しておくことで、あとで慌てずに済みます。
以下に帳簿のつけ方の記事をまとめました。

帳簿付けはクラウド会計ソフトを使う
副業の帳簿管理には、クラウド会計ソフトの活用がおすすめです。手書きやExcelよりも効率的で、収支の自動計算や自動記帳など便利な機能が豊富に揃っています。
freeeなどを使えば、確定申告もスムーズにおこなえます。
初期設定だけしておけば、日々の記録がラクになるので、忙しいサラリーマンに相性抜群です。
以下にクラウド会計ソフトの記事をまとめました。

控除や経費を活かせば、手取りが変わる
控除は、誰でも使える節税の基本ツールです。
知らないまま放置してしまうと、余計な税金を払うことになってしまいます。
- 「自分が使える控除はどれか?」
- 「確定申告で何を申請すべきか?」
このあたりを意識するだけでも、税金の負担感を軽減できます。
確定申告と年末調整
サラリーマンは、会社が所得税の計算と清算をおこなってくれる「年末調整」によって納税が完了します。
しかし、副業所得が20万円を超えた場合や年末調整でとれない控除を受けたい場合には、「確定申告」が必要になります。
年末調整とは?
年末調整は、会社が毎年12月に行う所得税の過不足調整です。
会社が1年間の給料から源泉徴収した所得税の合計額と、実際の課税所得に基づく税額を比べて、多く払いすぎていれば還付金として戻ってきます。
- 会社が手続きを代行
- 会社での給与所得に対してのみおこなう(副業所得は見ない)
- 一部の控除(基礎控除、配偶者控除など)は年末調整で完結できる
年末調整で取れる控除/取れない控除
| 年末調整で取れる控除 | 年末調整で取れない控除 (確定申告が必要な控除) |
|---|---|
| 基礎控除 配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 (iDeCoなど) 生命保険料控除 地震保険料控除 障害者控除 ひとり親控除 寡婦控除 勤労学生控除 住宅ローン控除(2年目~) | 医療費控除 雑損控除 寄附金控除 住宅ローン控除(初年目) 配当控除 上場株式譲渡損失との損益通算 |
確定申告とは?
確定申告は、1年間の収入や支出を自分でまとめ、税務署に申告・納税する手続きです。
副業や不動産、株取引などの給与以外の所得がある場合や医療費控除など年末調整では反映できない控除を取りたい場合には、確定申告をする必要があります。
確定申告が必要になるケース
- 副業の所得が年間20万円を超える
- 医療費控除を受けたい
- 寄附金控除(ふるさと納税)を使いたい(ワンストップ特例の場合は不要)
- 雑所得(暗号資産・ライター報酬など)がある
- 住宅ローン控除(初年目) など
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 実施者 | 勤務先 (会社) | 自分自身 |
| 対象 | 給与所得のみ | 副業、医療費、寄附金 など |
| 時期 | 毎年12月 | 翌年2月16日〜 3月15日(原則) |
| 利点 | 手間がかからない | 経費や控除を柔軟に 適用できる |
| 還付の 可能性 | あり | あり |
副業者にとっての確定申告
副業を始めたサラリーマンにとって、確定申告は避けては通れないステップです。
まずは基礎を理解し、税金の流れを把握することが、副業を長く続けていくための第一歩となります。


税務調査とは
帳簿のごまかしがありそうな申告や、稼いでいるのに無申告な人に対して調査をおこないます。
・提出された確定申告書が正しいか調査する
・無申告者に対して調査する
税務調査の種類
税務調査には、大きく分けて次の3種類があります。
- 簡易接触・・・電話や文書、呼び出しで話を聞く
- 実地調査・・・税務署から調査に来る(一般的に言われる税務調査がこれです)
- 強制調査・・・国税局査察部(マルサ)が令状を持って強制的に行う
税務調査が入りやすいケース
以下のような場合、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
- 売上と経費のバランスが極端
- 赤字続きなのに生活が派手
- 所得の申告漏れや副業収入の無申告
- 多額の現金取引や仮想通貨の取引がある
- 同業他社に比べて数字の動きが不自然
税務調査で大切な心構え
税務調査に対してポイントを意識することが大切です。
- 帳簿を日々しっかり記録する(領収書などを保管)
- 副業収入も含めて、正確に確定申告する
- 不明点があれば税理士などの専門家に相談する
税務調査でかかるペナルティ
税務調査で「申告漏れ」や「誤った経費処理」が見つかると、本税(本来納めるべき税金)に加えて、さまざまなペナルティ(追徴課税)が課されます。
ここでは、税務調査で課される代表的なペナルティを4つ紹介します。
① 過少申告加算税(10〜15%)
確定申告をしていたものの、本来より少ない金額を申告していた場合に課されるペナルティです。
指摘される前に自主的に修正すれば軽減されますが、調査で発覚した場合は10%、本税50万円を超える部分には15%が加算されます。
② 無申告加算税(5〜30%)
確定申告をまったくしていなかった場合に課されます。
税務署に指摘される前に自分から申告すれば5%程度に軽減されることもありますが、調査で発覚すると15%、さらに悪質なケースでは30%に引き上げられます。
③ 重加算税(35〜40%)
意図的に収入を隠したり、架空の経費を計上していた場合など、「仮装・隠蔽」と判断されると非常に重いペナルティが科されます。
通常のケースで35%、無申告に隠蔽が加わると最大40%の加算税がかかります。
④ 延滞税(最大14.6%)
本税の納付が遅れた場合に課される“利息”的な税金です。
支払いが遅れるほど延滞税も増えるため、申告後の納付はできるだけ早めに済ませるのがベストです。
これらのペナルティは本税に上乗せされるため、最終的な支払い額はかなり大きくなることも。
「副業だから大丈夫」は通用しません。正しい帳簿と申告が何よりの防衛策になります。
以下の記事に税務調査と追徴課税についてまとめました。

副業サラリーマンができる節税
副業で稼ぐと手取りが増えますが、稼いだ分だけ税金も増えます。
だからこそ、稼いだお金を効率よく守るために、節税の知識と実践が欠かせません。
節税とは、合法的に税金を減らす工夫のこと。
ズルをするのではなく、国が認めた制度を活用して、無駄な税金を減らす方法です。
副業サラリーマンにおすすめの節税術を紹介していきます。
ふるさと納税
実質2,000円の自己負担で全国の自治体に寄付ができ、寄付先から豪華な返礼品(お肉・お米・フルーツ・日用品など)がもらえる制度です。
寄付した金額のうち、限度額内であればほぼ全額が翌年の住民税から引かれるため、実質的には“節税しながらお得な買い物”ができるようなしくみになっています。
特に便利なのがワンストップ特例制度です。
これは、確定申告をしなくてもふるさと納税の税額控除が受けられる制度で、年に5自治体以内の寄付であれば申請書を提出するだけで手続き完了。
副業サラリーマンでまだ利益が上がっておらず、確定申告をしない人でも簡単に節税効果を得られます。
副業で利益が上がっていれば、確定申告が必要なのでワンストップ特例は使わないでおきましょう。
ふるさと納税は、節税と生活の充実を同時にかなえる制度です。
以下にふるさと納税の記事をまとめました。

また、ふるさと納税したのに税金が安くなっていないことがあります。
その理由を以下の記事にまとめました。

iDeCo(イデコ)
iDeCoは、老後資金を自分で積み立てながら、同時に節税もできる制度です。
最大の特徴は、毎月の掛金が全額「所得控除」の対象になる点。
これにより、所得税と住民税の負担が軽くなり、節税効果が得られます。
たとえば、月1万円を掛けた場合でも、年収や税率によっては年間2〜3万円程度の節税が可能。
長期的に見れば、数十万円以上の節税効果にもつながります。
iDeCoは月額5,000円からスタートでき、副業サラリーマンでも利用できます。
副業によって所得が増えて、所得税率が上がれば、より多くの節税につながります。
老後の備えと節税を同時に進められる、一石二鳥の制度です。
よく比較されるiDeCoとNISAの記事をまとめました。

医療費控除・生命保険料控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上、もしくは所得の5%を超えた場合に受けられる控除制度です。
本人だけでなく、家族の医療費も対象となるため、意外と多くの人が該当する可能性があります。
治療費、通院のための交通費、市販薬の一部も含まれる場合があるので、領収書はしっかり保管しておきましょう。
一方、生命保険料控除は、民間の生命保険・介護保険・個人年金保険などに支払った保険料が対象となる制度で、最大12万円(所得税)、7万円(住民税)までの控除が受けられます。
年末調整や確定申告で申請することで、税金が軽減されます。
どちらの控除も1月から12月に支払った額が対象になります。
以下の記事にまとめました。

青色申告特別控除
青色申告特別控除は、副業や個人事業で確定申告をする人が受けられる大きな節税メリットのひとつです。条件を満たせば、最大で65万円(電子申告などの条件を満たさない場合でも55万円)の所得控除を受けることができます。
例えば、副業で年間100万円の利益が出た場合、青色申告特別控除を使えば、最大65万円を引いた35万円分にだけ税金がかかる計算になります。これだけで所得税・住民税が数万円節約できることも。
この控除を受けるためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記による帳簿付けと申告が必要です。聞き慣れない言葉ですが、会計ソフトを使えば意外と簡単に対応できます。
副業収入が年間20万円を超える場合は申告義務もあるため、青色申告を選んでおくと将来的にもお得です。
青色申告特別控除について詳しくまとめました。

節税はズルではない
節税は、お金を増やすもう一つの手段です。
むやみに税金を払いすぎるのではなく、国が認めた制度を正しく使って、手取りの最大化を目指します。
副業と節税はせっとであることを常に意識しておく必要があります。
まとめ
税金というと難しそうなイメージがありますが、基本のしくみをおさえれば、手取り額や将来のライフプランに大きな差が出てきます。
特に30代は、収入が増えたり、結婚・子育て・住宅購入などのライフイベントが重なりやすい時期です。
そんなときこそ、「知らなかった」で損をしないための知識を身につけておくべきです。
- 自分が払っている税金の種類と金額を確認する
(給与明細を見て、所得税・住民税・社会保険料をチェック) - 副業を始めるなら、経費と確定申告の基本を押さえる
(必要経費の管理で所得税や住民税を減らせる) - 控除や節税制度を活用して、無駄な支出を減らす
(ふるさと納税・iDeCo・各種控除を駆使する)
税金や社会保険に関する知識は、副業・転職・投資など、あらゆる人生の選択肢に影響します。
今から少しずつ学びを深めて、お金と向き合うことが重要です。